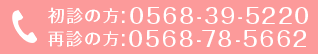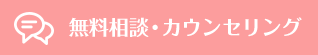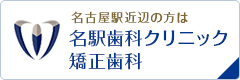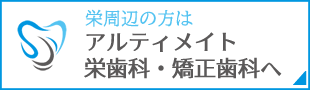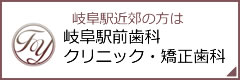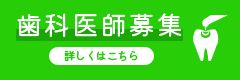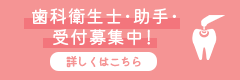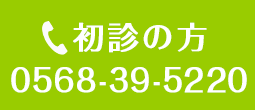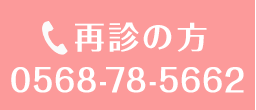前回は歯列矯正による見た目の変化について、考えられる理由を中心にお話ししました。
今回も同じテーマを取り上げて、主に対処法を紹介します。
歯列矯正による見た目の変化の一つに「ほうれい線の発生」があります。考えられる原因は、加齢や歯の大きな移動による頬のたるみの進行です。また歯ぎしりや噛みしめなどの悪習癖で、顔の周りの筋肉がむくんだり強張ったりすることも理由の一つです。装置を長期間付けて過ごした影響で、食事がしにくくなって表情筋が衰えた可能性もあります。ほうれい線は、さまざまな要因が絡み合って発生すると考えておきましょう。
老け顔になることを避けたい場合は、次の方法でケアを行ってください。口の中を粘膜で傷付けないよう、治療を完全に終えてから実施することが大切です。
1.顔のむくみ取りに有効な頬のマッサージ
①頬骨と小鼻の間に、人差し指の第二関節までを強く当てる。
②頬骨の下に沿う形で、こめかみに向かって少しずつ引き上げながら小さな円を描いて指を動かす。
③輪郭側にスタート地点を動かし、①~②を何度か繰り返す。
④顔のラインに沿って顔をマッサージすれば完了。
左右順番に行ってください。
2.ほうれい線の発生予防に有効な側頭筋マッサージ
耳の上からこめかみまでに伸びている筋肉を「側頭筋」といい、咬筋を支える役目を果たしています。
日頃から歯ぎしりや噛みしめといった悪習癖がある方は、側頭筋に負担がかかってほうれい線が発生しがちです。定期的にマッサージを行い、発生予防に努めましょう。
人差し指から薬指までの3本の指を側頭筋へ当て、前から後ろへ円を描きながら動かすだけでOKです。凝っていると感じた箇所は、とくに重点的に揉みほぐしてください。
3.口輪筋をトレーニングする
口腔周りにあるのが「口輪筋」で、ここを鍛えればほうれい線の改善が期待できます。
ほうれい線を伸ばすイメージで、口の内側から舌を動かしてみましょう!
口輪筋だけでなく舌の筋肉も鍛えられ、見た目のイメージ変化につながるかもしれません。筋肉によって舌の位置が変わり、口呼吸の予防にもつながるかもしれません。
口の中が渇きやすい方は、積極的にトライしてはいかがでしょうか?
歯列矯正が不安な方へ
歯列や咬合を整えられる一方、外見が悪化する可能性があると聞くと心配になりますよね。
周囲の知人やSNSのインフルエンサーの後悔の声を実際目や耳にして、怖いと感じている方もいらっしゃるでしょう。
ただ、すべての症例で外見が大きく変わるわけではありません。通常の歯列矯正は口腔内の部位へアプローチするので、大きな変化を起こす心配はまずないでしょう。
とくに見た目が変わりやすいのは、外科的処置や抜歯を要する場合です。
症例によって動くプロセスなどが異なるので、気になる方はかかりつけ医に確認してみましょう。口腔状態を診たうえで、起こりうるリスクなどをきっと教えてもらえるはずですよ。
抜歯をともなうケースについて
歯を大幅に移動する症例では、基本的に抜歯が必要です。その場合、見た目の変化がどうしても起こりやすいでしょう。
外科的処置をともなうケースについて
受け口や開咬、叢生といった重度の不正咬合が見られる場合、外科的処置が必要になるかもしれません。骨格にアプローチするので、見た目の変化が起こりやすくなるでしょう。